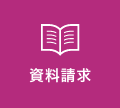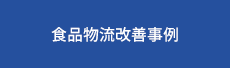現在、物流費の高騰が社会問題となっています。そのため、物流関係のビジネスで成功するには、この物流費高騰の理由を把握し、適切な対策をとることが必要不可欠です。
この記事では、物流費高騰の理由や今後実施すべき具体的な対策について詳しく解説します。読了後は、物流費を抑えるために今すべきことが見えてくるでしょう。物流業務にかかるコストを削減したい方や、企業負担を低減したい方は、今回の記事をぜひお読みください。
この記事では、物流費高騰の理由や今後実施すべき具体的な対策について詳しく解説します。読了後は、物流費を抑えるために今すべきことが見えてくるでしょう。物流業務にかかるコストを削減したい方や、企業負担を低減したい方は、今回の記事をぜひお読みください。
目次
そもそも物流費は何を指す?
物流費の高騰について見ていく前に、まず物流費そのものの意味をおさらいしましょう。物流費は「物流業務にかかる費用の総称」であり、「物流コスト」と呼ばれることも少なくありません。物流費は主に以下のような内訳に分かれており、具体的な比率は企業によって異なります。
輸送費:荷物の輸送時に必要となる費用
保管費:出荷前の荷物を倉庫で保管する費用
荷役費:入庫から出庫における業務に発生する費用
人件費:スタッフの雇用や教育にかかる費用
包装費:荷物の梱包を実施するための費用
IT関連費:業務効率化に向けたITシステムの利用のために支払う費用
この中でも特に高い割合を占める傾向にあるのが、「輸送費」です。というのも、荷物を輸送するにあたって長距離間を移動しなければならないことが関係しています。自社で輸送を行う場合も、外部の業者に委託する場合も、輸送費はほかの費用と比べて高額になりやすいでしょう。
物流費には、上記で取り上げたもの以外にもいくつか種類が存在します。以下の記事では、代表的な費用のほかに、意外と見落としがちな費用についても説明していますので、あわせてご確認ください。
関連記事:「物流コストとは?費用の具体的な内訳についても細かく解説」
物流費が高騰する理由は?

ここからは、物流費が高騰している具体的な理由について見ていきましょう。現在における物流費の高騰は、下記のような理由が複合化して発生していると考えられています。
- 物流業界の労働力不足
- 燃料費の高騰
- 消費者からの需要増加
- 都心部における物流の整備不足
①物流業界の労働力不足
まず取り上げるべき理由の一つは、物流業界全体で人手不足が発生しているということです。荷物の配送を担当するトラックドライバーが不足している状態で物流業務を遂行しなければならないため、人件費が跳ね上がっています。
こういった状況に陥ってしまった要因は、トラックドライバーの時間外労働時間の制限が関係しています。というのも、ドライバー一人当たりの労働時間が限られてしまうことから、より多くの雇用が必要になるからです。なお、これは「2024年問題」とも呼ばれており、物流業界全体の大きな課題でもあります。
こういった状況に陥ってしまった要因は、トラックドライバーの時間外労働時間の制限が関係しています。というのも、ドライバー一人当たりの労働時間が限られてしまうことから、より多くの雇用が必要になるからです。なお、これは「2024年問題」とも呼ばれており、物流業界全体の大きな課題でもあります。
②燃料費の高騰
燃料費の価格が上昇することによって、物流費全体も多大な影響を受けます。なぜなら、燃料費は物流コストの中でも大きな比率を占める輸送費の中に含まれるからです。
この値上げは戦争・紛争の勃発や感染症の流行をはじめとした世界情勢の変化が原因だといわれています。これによって物流業務における企業の負担が大幅に増えるため、価格高騰への対策は必須となるでしょう。
この値上げは戦争・紛争の勃発や感染症の流行をはじめとした世界情勢の変化が原因だといわれています。これによって物流業務における企業の負担が大幅に増えるため、価格高騰への対策は必須となるでしょう。
③消費者からの需要増加
物流費の高騰は、消費者からの需要が増加したことも関係しています。EC市場が活性化したことにより、オンラインショッピングの人気が高まったことが、主な原因といえるでしょう。
こうして増加した大量の注文をカバーするためには、スタッフを増やさざるを得なくなります。しかし、現在は物流業界全体が人手不足であるため、人件費の価格が上昇。それが結果的に物流費の高騰につながってしまうのです。
こうして増加した大量の注文をカバーするためには、スタッフを増やさざるを得なくなります。しかし、現在は物流業界全体が人手不足であるため、人件費の価格が上昇。それが結果的に物流費の高騰につながってしまうのです。
④都心部における物流の整備不足
人が多い都心部は、特に物流の需要が高まるエリアです。しかし、都心部の施設やシステムには、物流を優先させた仕組みが完備されているとはいえません。
こうした状況により需要と供給のバランスが崩れ、物流そのものがキャパオーバーとなってしまうので、物流の整備不足をまかなうための業務効率化が必須となります。
上記のような理由が複数存在することを考えると、物流費の削減は難しいと考えられています。「物流コストを削減しよう!効果的な実例や気をつけるべきポイントも紹介」では、そういった物流コスト削減の難しさについて解説していますので、関連情報としてぜひお読みください。
こうした状況により需要と供給のバランスが崩れ、物流そのものがキャパオーバーとなってしまうので、物流の整備不足をまかなうための業務効率化が必須となります。
上記のような理由が複数存在することを考えると、物流費の削減は難しいと考えられています。「物流コストを削減しよう!効果的な実例や気をつけるべきポイントも紹介」では、そういった物流コスト削減の難しさについて解説していますので、関連情報としてぜひお読みください。
物流費の高騰を防ぐためにするべきこと

物流費が高騰する理由には、さまざまな種類が存在することがわかりました。それでは、物流費の高騰に対応するためには何をすればよいのでしょうか。この段落では、特に代表的な4つの対策について説明します。
- 物流拠点をコンパクト化する
- 在庫状態を適正化する
- DX化によって業務効率を向上させる
- 物流業務を業者に依頼する
①物流拠点をコンパクト化する
複数存在する物流拠点をコンパクトにまとめることで、設備維持にかかる料金やスタッフの人件費を削減することが可能です。少ない拠点に機能を集約させたほうが、在庫管理をはじめとした物流業務が進めやすくなるという利点もあります。
まずは各拠点にかかっているコストをリサーチし、拠点数を減らすための準備を進めましょう。
まずは各拠点にかかっているコストをリサーチし、拠点数を減らすための準備を進めましょう。
②在庫状態を適正化する
もし在庫が過剰状態にある場合は、在庫を適正化することも重要です。在庫が余剰してしまうと、無駄な廃棄費用が発生するリスクがあります。これまでの販売データをもとに今後の発注数を予測し、適切な状態を維持しましょう。
③DX化によって業務効率を向上させる
物流業務をDX化することで、少ない人員の中でも必要な業務を完了させることができます。DX化における具体的なシステムとしては、下記が例に挙げられるでしょう。
- 配送管理システム(TMS)
- 倉庫管理システム(WMS)
- 電子データ交換システム(EDI)
- ロボットによる業務自動化システム
こういったシステムを現場に導入する際は、「システムに精通したIT人材も合わせて採用すること」が重要です。そうすることで、導入したシステムの形骸化を防ぐことができます。システムを取り入れるだけではなく、結果を出すための施策もあわせて実施するようにしましょう。
④物流業務を業者に依頼する
物流業務を業者にアウトソーシングすることで、設備の維持費・スタッフの人件費・業務上の手間などをまとめて削減することが可能です。この結果、自社のリソースを別の業務に注力することができ、業績アップにも結び付いていくでしょう。
アウトソーシングには別途コストがかかりますが、毎月発生するコストが明確化できるという利点があります。物流費高騰にも対応しやすい環境が作れるので、アウトソーシングを導入する価値は大きいでしょう。
関連記事:食品物流のアウトソーシングとは? 導入メリットから選び方まで解説!
アウトソーシングには別途コストがかかりますが、毎月発生するコストが明確化できるという利点があります。物流費高騰にも対応しやすい環境が作れるので、アウトソーシングを導入する価値は大きいでしょう。
関連記事:食品物流のアウトソーシングとは? 導入メリットから選び方まで解説!
物流費の高騰を見込んだうえで早めに対策をしよう
物流費が高騰し続けることは、今後避けられないと考えられています。そのため、早めに「物流拠点をコンパクト化すること」「在庫状態を適正化すること」などの対策に取り組むことが重要です。
また、現状を改善するために「受注時間をできる限り前倒しし、他社の荷物と混載できる状態にすること」「DX化を推進することによって、業界全体のリソースを拡大すること」などに力を入れることも大切です。こうして物流業界に属する立場の者たちが、今自分たちにできることを考えて行動に移せば、業界全体における高騰対策の充実につながっていくことでしょう。
また、現状を改善するために「受注時間をできる限り前倒しし、他社の荷物と混載できる状態にすること」「DX化を推進することによって、業界全体のリソースを拡大すること」などに力を入れることも大切です。こうして物流業界に属する立場の者たちが、今自分たちにできることを考えて行動に移せば、業界全体における高騰対策の充実につながっていくことでしょう。
食品物流・食品配送なら北王GROUPにおまかせください
もし物流コストについて悩みがある場合は、首都圏の食品配送に関するノウハウを積んできた北王GROUPにご相談ください。
北王GROUPでは、より効率よく荷物が配送できる「食品共同配送サービス」や物流業務を一括でアウトソーシングできる「食品3L」を提供しています。これらを利用することで、物流費の高騰に対応可能な状態が形成できるでしょう。
また、食品物流における充実した環境が整っていることも北王GROUPの特徴です。3温度帯対応の食品物流センター・食品倉庫を関東エリアで7つ運営しており、その規模は10,000坪を超えています。
首都圏や関東圏の食品配送をより効率化するためのサービスをご検討中なら、まずはお見積もりからご依頼いただけますと幸いです。資料請求も承っていますので、気になる方はぜひ以下のページをご覧ください。
北王GROUPでは、より効率よく荷物が配送できる「食品共同配送サービス」や物流業務を一括でアウトソーシングできる「食品3L」を提供しています。これらを利用することで、物流費の高騰に対応可能な状態が形成できるでしょう。
また、食品物流における充実した環境が整っていることも北王GROUPの特徴です。3温度帯対応の食品物流センター・食品倉庫を関東エリアで7つ運営しており、その規模は10,000坪を超えています。
首都圏や関東圏の食品配送をより効率化するためのサービスをご検討中なら、まずはお見積もりからご依頼いただけますと幸いです。資料請求も承っていますので、気になる方はぜひ以下のページをご覧ください。